アノマリーだから実現できる“クライアントフュージョン”──支援の枠を超えたマーケティングを小田さんにお聞きしました

マーケティングは「誰とどこまで向き合えるか」が大切です。
どんなに精密な広告運用をしても、クライアントのことを深く理解できなければ、本当に効果のある施策は生まれません。アノマリーマーケティングさんは、クライアントと徹底的に向き合い、まるで「フュージョン」するように事業を成長させていくスタイルを大切にしています。
「ただ広告を回すだけでは物足りない」「もっと本質的なマーケティングに関わりたい」と考えている方には、ぴったりの環境かもしれませんね。
今回は、小田さんにその戦略や働き方、そして一緒に挑戦する仲間に求めることについて、お話を伺いました!
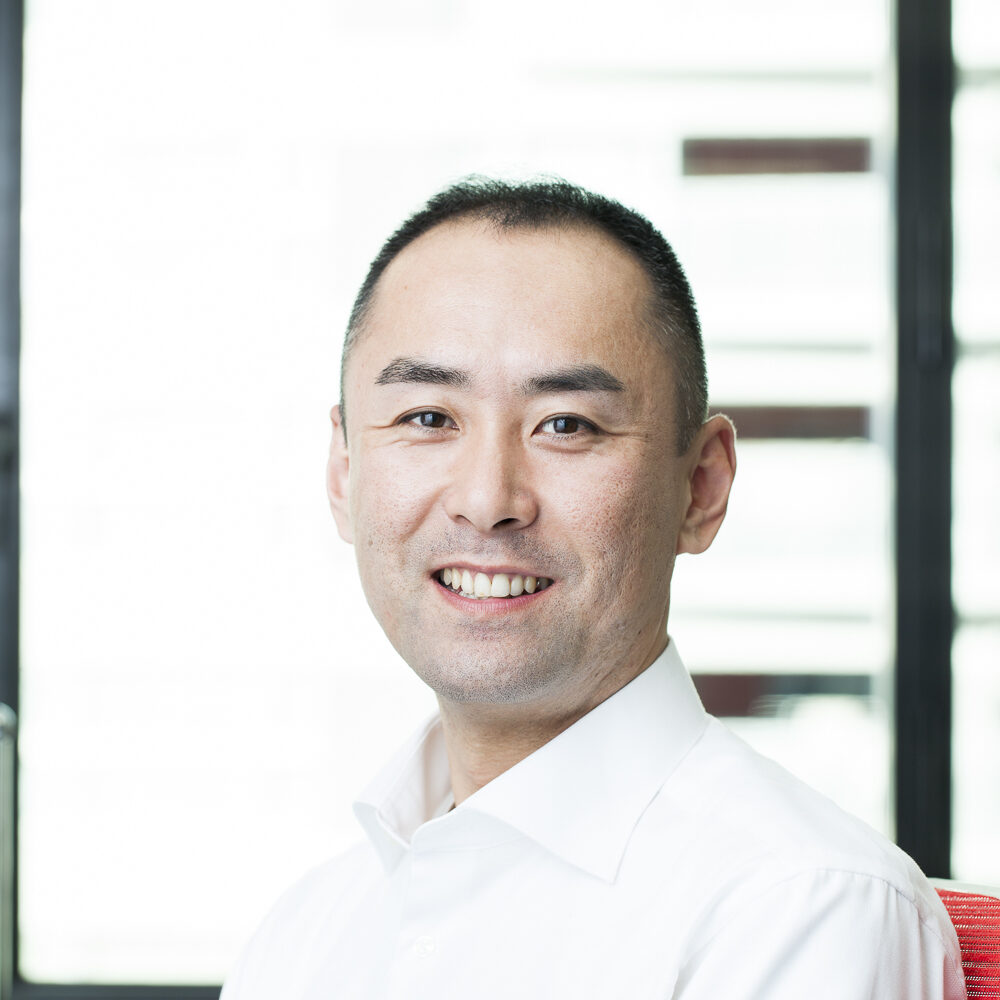
インタビュアー:運営堂 森野誠之さん
2006年よりフリーランスでウェブマーケティング支援業を開始。Google アナリティクス・Googleタグマネージャーを黎明期から継続的に活用して、中小企業や制作会社の改善支援に携わる。Web制作から解析、SEO、SNS運用、社内体制づくりまで、現場の課題に寄り添う「幅広く、それなりに深い」アプローチが持ち味。セミナー登壇や取材、執筆も多数。現在は名古屋と徳島の二拠点生活を送りながら、平日毎日配信のニュースまとめメルマガをはじめとする情報発信を軸に、「信頼されるWebの相談相手」として活動中。
HP:https://www.uneidou.com/
Twitter:@uneidou
アノマリーマーケティングの由来
 森野
森野今日は、アノマリーマーケティングの小田さんに、会社についていろいろお伺いしたいと思います。最初に「アノマリー」という言葉の意味ですが、「変わった」や「異質な」といったニュアンスがありますが、どういう意味の言葉なのでしょうか?社名の由来とあわせて教えて下さい。



直訳すると「異常」や「常軌を逸した」といった意味です。社名の由来にはいくつか理由があるのですが、大きく分けて2つあって、1つは「A」から始まる名前にしたかったんです。周りに「A」から始まる会社が多くて、リスペクトの意味も込めて、「A」で始まる単語を探すのが早いかなと考えました。
全部調べてみて、自分たちがやりたいことや会社の意義に合うものをいくつか絞り込んだ結果、「アノマリー」が一番しっくりきたんですよね。



昔は電話帳で最初に来るから「あ」から始まる社名が多かったんですが、そんな古い理由ではなかったんですね(笑)。2つ目の理由も教えて下さい。



「アノマリー」という言葉は投資用語としても使われていまして、その世界では「理論的には説明できないけれど、経験的にはそうなる傾向があるとされる規則性」のことを「アノマリー」と呼んでいます。これがマーケティングにも通じると感じたんですよね。
マーケティングも、すべてが理論通りにいくわけではなく、経験や直感、タイミングによって成果が大きく変わることがありますよね。そういった意味で、「アノマリー」という言葉がぴったりだと思い、「アノマリーマーケティング」という名前にしました。



マーケティングにはたくさんの理論がありますが、実際にやってみると必ずしもその通りにはいかないですよね。あとになって思うとそうだったかも、ということはあっても、人間がやることなので理屈通りの型にはまった動きにはならないですよね。



「こうやるべき」という理論はあるものの、実際にはクライアントごとに異なる結果になることも多いですよね。社名に「マーケティング」とつけたのは、外から見てわかりやすいほうがいいと思ったからなんです。ただ、ひとつだけ後悔していることがあるとすれば、少し名前が長くなってしまったことですね。



そこは仕方ないですよね。「アノマリー」だけだと意味が広すぎて、何の会社かわかりにくくなってしまいますし、モノポリーみたいで意味が伝わりませんし。



実は「アノマリー」という名前の会社もすでにありましたし、SEOの観点からも、あまり適当につけすぎると後から「しまった、どうしよう…」となることもありますからね。
アノマリーマーケティングさんがやっていること



マーケティングに関しては、ウェブに限らず幅広い分野を対象にしているということでしょうか?



ウェブ広告の支援や運用代行がメインです。広告だけではクライアントの成果が十分に出ないこともあるので、ウェブ広告に限らず最適なウェブマーケティング施策を幅広く支援していますが、「ウェブマーケティング全般」としてしまうと、クライアントも具体的にどんな相談をすれば良いのか分かりにくいと思いますし。



「ウェブマーケティング全般」を掲げている会社はたくさんありますよね。制作会社さんでもやっているとうたっているところはたくさんあります。その中で、「ここは他と違う」と言えるような強みや特徴は何かありますか?



やっていることは他の会社と大きく変わらないと思います。我々が一番大事にしているのは「クライアントの理解」です。現在、「クライアントフュージョン」 という概念を定義しているところなんです。ドラゴンボールが好きな方ならイメージしやすいと思うのですが、クライアントと息をぴったり合わせないと、本当の成果は出ないよね、という考え方ですね。
まだ作り上げている途中なのでうまく説明しきれないのですが、近いうちにリリースする予定です。それを見てもらえれば、より伝わりやすいかなと思います。
クライアントフュージョンについて整理しました!



多くの会社は、依頼を受けて広告のアカウントを作成し、広告を出すだけで、あまり深いやり取りはしないですよね。もっとクライアントに深く入り込んで伴走するようなスタイルでしょうか?



そうですね。我々はもっとクライアントに深く入り込み、しっかりと伴走する形をとっています。クライアントフュージョンの具体的な中身としては、「コミュニケーション」と「事業理解」を徹底的に行うことを重視しています。仕組み化して明確な定義とプロセスを作ることで、「この方法でしっかり成果を出します」という形を整えているところです。料金に関しても、ウェブ広告運用の場合は広告費に対してのフィーという一般的なモデルなのでわかりやすいと思います。



ここは他社と比べても、かなり大きな差別化ポイントになると思います。



結局のところ、広告運用だけでは十分な成果が出ないと我々も分かっているので、その先までしっかり見据えています。クライアントの事業を深く理解していないと、適切な提案もできませんし、実行までつなげることも難しいですよね。
最初は小さな取り組みから始めて、「相性が合うか」「自分たちに任せられそうか」を感じてもらった上で、さらに深く関わっていくという形をとっています。フリーミアムではないですが、それに近いスタイルですね。ウェブ広告に限らず、コンテンツ制作やリアルな施策、例えば交通広告の出稿、看板、チラシ配布など、幅広い手法で支援しています。
成果重視と顧客重視のバランス



なるほど。成果を重視する一方で、「顧客最適」という考え方もありますよね。成果を優先しすぎると顧客がついてこなかったり、顧客の方針によって動きづらくなったりすることもあると思います。そうした場合、成果重視と顧客重視のバランスはどう取っていますか?



成果を出すことは重要だと考えていますが、前提として「クライアントにとって最適な方法で」という点は絶対に守るべきだと思っています。実際に取り組んでみると、このバランスを取るのは非常に難しいと感じていて、カルチャーとして浸透させなければ単なる理念で終わってしまい、機能しなくなってしまいます。



クライアントからしたらカルチャーの前に「何百万円か投資して、結局いくら売れるの?」というシンプルな疑問に行き着いちゃうんですが、そこはどう考えていますか?



僕としては「一緒に頑張って成果を目指したい」と思えるクライアントと仕事をしたいので、双方が選び合う形でいいのかなと考えています。価値観を共有できるクライアントには、しっかりコミットしたいという想いがあります。
もちろん、この考え方を理解していただけない場合もあって、お断りすることもありますね。「成果が見込めない」「ウェブ広告が最適な手段ではない」「考え方が合わない」など理由は様々なのですが。
具体的にやることは?



やはり相性が合うことが前提で、その上でクライアントの要望をしっかり聞きながら、成果を出していく形になりますね。
具体的にやっていくこととしては、広告を出稿して、LP(ランディングページ)を作成して、さらにバナーやLPのクリエイティブを改善していく、という流れになると思います。こうした施策が基本となりますが、これだけで成果が出るというわけではないですよね?



もちろん、成果が出ないこともあります。状況が良くない場合には「なぜ成果が出ていないのか」を明確に伝えた上で、クライアントと相談しながら進めていくことが大切だと思っています。クライアントの予算やさまざまな事情も考慮しつつ、バランスを取りながら最適な形を模索していく、というスタンスですね。
本当に深く関わる場合は、「サービスの内容をこう変えましょう」「料金設定を見直しましょう」といった根本的な部分まで踏み込んで提案することもあります。



管理画面の調整やクリエイティブの改善だけでは大きな変化を生み出しにくい部分もありますよね。



正直なところ、広告の管理画面はほとんど見ていません…というのは言い過ぎかもしれませんが、しっかり設定されていれば頻繁にチェックする必要はないですし、管理画面を操作するだけでは成果にはつながらないと考えています。
LPについても改善を重ねますが、一定期間配信しないとデータが十分に集まらないため、スケジュールを決めて改善を繰り返していくことが重要になります。このあたりは当たり前に行っていて、より深い部分まで踏み込んで改善していく必要があるという考えですね。



競合もいろいろやってきますしね。



そうですね。他の広告代理店も同じような施策はやっていると思うので、より成果に直結する部分から取り組まないと、我々の強みも活かせませんし、成果も出にくいと感じています
成果を出すために徹底的な調査



その中でいろいろ競合が出てきたり、料金変えようと思ったら調査をしないといけないですよね。そのときはどうしていますか? ネットで調べる方法もあれば、具体的に使うとか買うとか、インタビューとか、いろいろあると思うんですけど。



実際に体験できるものは、支援を始める前に自分たちで体験しますし、必要であれば購入することもあります。クライアントの展示会に足を運んだり、営業に同行したり、接客の現場を見に行ったりと、可能な限り一次情報を取りに行くことを意識しています。
成果を出すには一次情報が不可欠なので、それに近い情報をどう集めるかが重要ですから、できることはすべてやるというスタンスですね。



受注前にここまでやるんですか?



受注前はできる範囲での調査になります。商品であれば購入して試すこともできますが、すべてのケースで深く入り込めるわけではないので、その範囲内でリサーチしながら提案していく、という形ですね。



受注前に何でもかんでもやってくれると思ったら、それは違うってことですね。クライアントとしっかりコミュニケーションを取って、関係がうまく築けた上で営業同行などができると思いますし。



そうですね。展示会などは「行きます」と言ってしまえば、実際に行くこと自体は難しくないですし、嫌がられることもありません。クライアントと密にコミュニケーションを取りつつ、その延長線上で自然に行うイメージですね。 このあたりもできる範囲で進めることが大切で、あまりやりすぎると方向性がブレてしまうこともあるので、バランスを取りながら進めるようにしています。
コミュニケーション力がすごい



これをする、あれをすると決めるのではなくて、状況を見ながら必要な情報を集めて実行していく。このあたりの塩梅って難しいですよね。クライアントとコミュニケーションを取る際は、オンラインと対面の両方を活用するイメージですか?



個人的に対面で会うのが好きなので、行ける範囲ならできるだけ直接会いに行くようにしています。僕の立場だからこそできることかもしれませんが、プライベートで旅行に行った際に、クライアントのところへ立ち寄ることもあります。



どちらかというと、ビジネスライクな関係というよりは、自然と仲良くなるようなスタイルですね。



クライアントは「仲がいい」と言える関係の方が多いですね。信頼もしてもらえていると感じますし、その上でしっかり成果を出せれば最高だなと思っています。どこまで仲良くなるべきかは難しいところですが、やはり仕事としての線引きは必要だと考えています。



コミュニケーションお化けみたいな感じなのですが、実際はどうなんでしょうか?



いやー、特別コミュニケーション能力が高いわけではないので、時間をかけてクライアントのことを理解しながら、同時にこちらのことも理解してもらう、といった形で関係性を築いていくのが好きですね。
クライアントの人材育成も



少し安心しました(笑)。
取り組まれていることの中心がウェブ広告とのことですが、その割合はどのくらいのイメージでしょうか?例えば、ウェブ広告が全体の7割や半分といった比率になるのでしょうか?



おっしゃる通りで大体7割くらいかなと思います。 残りの割合はその時々で変わりますが、多いのはウェブマーケティング全般の支援ですね。イメージとしてはコンサルティングに近いものです。
また、インハウス支援のご相談も増えていて、同業のウェブ系代理店の支援や、業界を問わずマーケティング部署を立ち上げたい企業のサポートなども多いです。特に今年からは、お客様の会社から2名が当社に出向するという新しい取り組みが始まりました。当社のメンバーは2名なのでちょっと不思議な状況ですが(笑)。これは「クライアントフュージョンしすぎているインハウス支援(?)」とも言えるのかなと思っています。
下記の記事でこちらの事例を公開しております!
⇒出向で事業会社の悩みを解決!?「広告運用の専門家不在」を解消するアノマリーな取り組み事例



確かにしすぎている感じがします(笑)。大きな企業だと「越境学習」のような仕組みがありますよね。出向に近い形で1年ほど修行して戻ってくるものです。ただ、短期間でいなくなりますし、任せる仕事も難しそうですが。



こちらとしては大変ですね。ただ、一緒に仕組みを整えながら学ばせていただくこともあると思いますし、単純に「やったことがないからやってみるか」という気持ちもあります。 まだ始めたばかりなので、これからどうなるか、といったところですね。



Yuwaiの田中さんも、この業界で教育がなかなかうまくいかないとインタビューで答えてましたけど、狭い知識になってしまうし、先輩もいなくなったりするし、しっかり学ぶことってなかなか難しいですよね。



個人的にはスキルは能動的に取りに行かないと成長しづらいと考えています。会社としてはしっかり仕組みがあった方がいいと思うものの、ある程度の主体性がないと厳しい業界なのかなとは思いますね。
独立したい!ぐらいのやる気がある人が合う会社



そんな状況の中で、社内には2名いらっしゃるとのことですが、どのように育成を進めているのでしょうか?



教育については、現時点で明確な仕組みがあるわけではなく、そこも作りながら進めているというのが実情です。 基本的には「自分で学んでいってね」というスタンスが理想ですが、考え方など必要なことはしっかり伝えつつ、実務を通じて学んでもらう形をとっています。それにも限界があるので、運用者として一人前になれるように育成することを軸にしています。現在はカリキュラムがあり、それに沿ってOJT形式で教えているというところですね。



まずはウェブ広告の運営者として一人前になって、そこから次があるというイメージですね。



そこができたら営業の動きも教えつつ、ウェブマーケティングの他の施策についても学んでもらう形ですね。この段階までいくと、自然と自分の興味のある分野を見つけて広げていくパターンが多いですけどね。
僕らが教えるのは主にウェブ広告と営業の部分で、営業もそのまま担当してもらうつもりです。具体的には、問い合わせが来たら運用者がそのまま営業対応する形ですね。



アノマリーマーケティングさんに入りました、何すればいいですかとか言っている人はちょっと厳しくて、こういうことやりたいから来た、じゃないといけないですね。



「独立したい!」くらいの気持ちで来てくれると、成果を出しやすいと思いますし、最終的に独立してもらえたら僕もすごく嬉しいですね。在籍している間は、会社として成し遂げたいことにしっかり協力してもらいながら、一緒に成果を出していこうというスタンスでやっていますから。



独立したら嬉しいというのはなぜ?



それくらいの気概がないと成果は出ないと思うんですよね。あとは、辞めるのであれば前向きな辞め方をしてほしいという気持ちもあります。「合わなかった」という理由で辞めるのは採用の問題かもしれませんが、ネガティブな辞め方よりも、次のステップにつながる辞め方のほうが嬉しいです。ちゃんとウェブマーケティングができる人が増えて、「うちの会社がそこに何かしら貢献できた」と思えたら、個人的にはすごくやりがいを感じます。
今はベースの給料+コミットラインがあって、一定の粗利を超えると、その超過分の何%かを給与として支払う形になっています。退職後も活用できる仕組みにできないかと考えていて、例えば「辞めた後もそのままお客様を担当していただいて、粗利の半分をフィーとしていただく」という形にすれば、アカウントをそのまま使ってもらえて、お互いにメリットがあるのかなと。



例えば「独立初年度はフィーをもらって、何年目からはなしにする」といった仕組みにするイメージですね。辞めた後に業務だけが残ってしまうと、単純に負担が増えるだけになってしまいますし。
人を抱えて、仕事を定型化して量で回す、みたいなやり方はまったく考えていないですか?



その形の仕組化は考えていないですね。そもそもはある程度の規模までは大きくしないと、自分たちがやる意味がないとも考えています。具体的な人数は決めていませんが、10人程度の少数精鋭で、しっかりクライアントに成果を出せる体制を目指しています。 個々の強みを活かしながら動ける環境を作りたいですし、属人性があったほうが効果的な場面も多いので、結果的に個々の裁量が大きいスタイルになるかなと思います。



イメージとしては、そこそこの規模になって、小さいコンサル会社のような形ですね。 そうなると、働きたい人はどれだけでも働いてしまうので、一般的な雇用形態では少し難しい部分が出てくると思います。そのあたりの仕組みはどのように考えているのでしょうか?



今は定時を設けていますが、最終的な理想は裁量労働です。制度上難しければフレックス制を取り入れ、「成果を出せばしっかり稼げる」形にするのが現実的かなと考えています。極端な話、働く時間が少なくても成果を出せていれば問題ないと思っています。
その一方で、成長には一定の負荷が必要なので、そのバランスをどう設計するかが課題ですね。
名古屋でしっかりと成果が出せる会社にしたい



なるほど。今後はそういった人を増やして、ウェブマーケティングの分野でもっと存在感を高めていく、というイメージでしょうか。



自分が住んでいる場所がもっと盛り上がったら嬉しいなとは思っています。クライアントは全国にいますが、名古屋に拠点を置きながら成果を出し、「しっかりウェブマーケティングをやっている会社」として認知されることで、地域貢献といった意味合いも生まれるのかなと。



地方でウェブマーケティングをやりたい人にとって、いきなり東京に行くのはハードルが高いですよね。そう考えると、名古屋やその周辺で経験を積める環境があるのは意味があると思います。アノマリーマーケティングさんに来て修行し、独立してもらうのも歓迎なわけですから。



こういった会社はそれほど多くないと思うので、しっかり学びたい方の受け皿になれたらいいなと考えています。



そう考えると、やはり来てほしいのは、ある程度若くて、やる気のある人でしょうか?



自分自身、今35歳なんですが、30歳を超えて昔のようには働けなくなってきたと感じることが増えました。「まだ若いのに何を言っているんだ!」と思われるかもしれませんが(笑)。振り返ると「20代のうちに頑張ったから今があるな」と実感することが多いんです。だからこそ、20代でしっかり努力したいと思っている人とは相性がいいと感じます。
もちろん、キャリアがある人も歓迎ですし、今のフェーズではとてもありがたい存在ではあります。



地方で働きながらも東京まで行って大きくキャリアアップしたいわけではなく、適度なレベルでやっていきたいという人もいますよね。
「給料が安いのは嫌だけど、ちょうど真ん中くらいのポジションで働きたい」という人たちは受け入れの可能性はありますか?



ある程度の目安となる成果を設定していて、その成果を達成できれば会社としても一緒に取り組む意義があると考えています。どの程度が「ちょうどいい」のかは人それぞれですが、地方で「適度なレベルで働きたい」という人にとって、大きくズレた環境ではないのかなと思います。
独立してくれると嬉しいとは言いましたが、全員にとってそれがゴールとは限りませんしね。



そうですよね。自分のやりたいことはいろいろあるので、会社としてもできるだけそれに合わせたほうがいいですし。ただ、ある程度の成長意欲や学ぶ姿勢が必要だという条件付きだと思いますけど。
働き方についてはフルリモートOKなのか、フル出社なのかどのようになっていますか?



今はフル出社ですね。僕もフル出社しています。まだ3年目の会社ですし、会社の仕組みづくりなども一緒に進めていく必要があるので、実際に顔を合わせて進めないと難しい部分が多いですね。
ウェブマーケティングが好きな人に来てほしい



リモートでちょっと管理画面を見たり、ネット上で軽く対応するだけだと仕組み作りは難しいですよね。ゆくゆくはハイブリッドなどもあるぐらいで。
こんな人に来てほしい!というイメージはありますか?



ウェブマーケティングが少しでも「好き」であってほしいですね。単なる手段としてではなく、その先にある価値を見据えている人が理想です。
うまく言語化しづらいのですが、僕自身も人が好きで、ウェブを介してさまざまなことができるからこそ、ウェブマーケティングが面白いと感じています。手段としてのウェブマーケティングが好きというより、その先の目的を持っている人と働けたら楽しいですね。
「ウェブマーケティングを活用してしっかり稼ぎたい」でもいいですし、「クライアントに貢献したい」といった思いでも構いません。何かしら自分なりの目的を持っている人と一緒に仕事ができると、より面白いと感じます。



わかります、わかります。
単にSEOの手法や広告運用のテクニックとして、「これをこう変えたら成果が上がる」といったことではなく、もっと本質的に顧客やユーザーを理解するのが好きな人ですね。「こういう人がいるから、こんな施策を試してみたら面白いんじゃないか?」と考えられるようなタイプの人と一緒に働きたい、ということですね。



結局のところ、仕事は人と人の関係だと思っています。「SEOを極めたい!」というのも素晴らしいことですし、それ自体はまったく問題ありません。僕としては、人に興味を持ち、相手のことを考えることが好きな人のほうが、より相性がいいかなと感じています。



Googleのアルゴリズムをハックするのではなく、ユーザーに寄り添った記事を書いて、それをうまく活かせる人が良さそうですね。アフィリエイターであっても、単にシステムや数字だけを見ている人ではなく、ユーザーのことをしっかり理解して取り組んでいる人なら問題ない感じです。
本日はありがとうございました。
インタビューを終えて
運用型広告の運用者はキャリアが行き詰まりがちですよね。ウェブでやれることは限られていますし、仕組みもAIがメインになっていますから。そんなときにキャリアの幅を広げられるのは、さまざまな施策を素早く実行してしっかりと成果の出せる小さな会社だと思います。大きな会社だとやれることに制限がありますし、クライアントの意思決定に時間がかかってしまい、結果的に成長も遅くなりますので。
名古屋に通うことができて、ウェブも含むマーケティング全般のキャリアアップをしたい方は、アノマリーマーケティングさんがいいかもしれません。もちろん、じっくりと腰を据えて地域に貢献したい人も。
